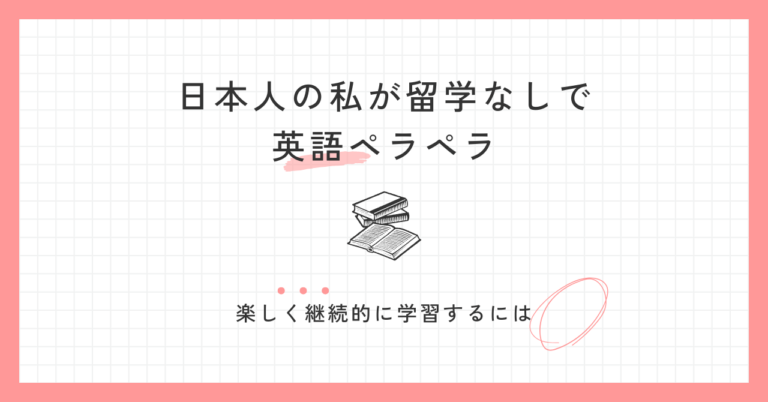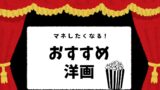皆さんこんにちは!ハニーです。
「英語を話せるようになりたいけど、どんな風に勉強すればよいのか分からない…。」そんな風に悩んでいませんか?
留学や外国人が沢山いる街に行けたらよいけど、みんながそんな機会に恵まれるわけじゃないですよね。
私も田舎在住、留学なしで英語が喋れるようになるためにいろいろ模索しましたが結局これだよねという結論に至ったのでそれを説明していきたいと思います。
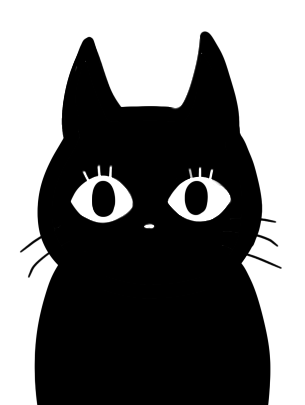
この記事は次のような人におすすめ!
・英語をしゃべれるようになりたい方
・英語の勉強法を模索している方
ここで意識していただきたいのは、私のやり方のイメージは、「勉強」ではなく「学習」だという事。
ポイントは「楽しく、継続的に」取り組むこと。
そして、教材だけに頼らず、日常的に触れられる洋画や洋楽を活用することです。
具体的な方法やその理由についても詳しく説明します。
それでは、どうぞ♡
洋画のキャラをマネする
ただつまらない教材を音読するより、自分の好きな俳優さんやキャラクターのマネをした方が遥かに頭に入ると思いませんか?
勉強が全く頭に入らないのは、シンプルに面白くない・興味がないからだと思っています。
さらに、映画は日常会話で使えるフレーズを学べる絶好のツールです。
それなら、活用しない手はないですよね。
ただし、ただ漠然と見るだけでは効果が薄いので、次のような流れで進めるのがおすすめ!
ステップ1:日本語字幕で一度観る
まずは映画の内容を把握!
日本語字幕で観てストーリーを理解しましょう。
特にお気に入りのシーンを見つけておくと、後の練習がより楽しくなります。
ステップ2:英語字幕で再視聴
次に、英語字幕で同じ映画を観ます。
このとき、気に入ったセリフや「使えそう!」と思うフレーズに注目し、出来ればシャドーイングをしながら見ましょう。
ステップ3:あとはセリフをひたすらマネ
セリフを口に出して何度もマネしてみましょう。
ここで重要なのは、ただ口に出すのではなくそのキャラクターになりきって喋る事です。
感情を込めて話すことで、イントネーションやリズムを身につけます。
ステップ4:繰り返し視聴して耳を慣らす
同じ映画やシーンを何度も観ることで、自然とフレーズが頭に残りやすくなります。
「聞く→マネする→繰り返す」の流れを続けることで、少しずつ自分のものになります。
好きな映画を見ることがおすすめなのは、繰り返し見ても飽きないようにするためです。
洋楽で学ぶ英語
音楽は、リズムと一緒に英語を覚えられるので非常に効果的!
さらに多くの人は意識しなくても、音楽は何度も聴き口に出すんじゃないでしょうか?
それを利用して是非英語も身に着けちゃいましょう!
ステップ1:好きな曲をひたすら聞く
まずは自分の好きな曲を選びましょう。
モチベーションが高まるので、学習が楽しくなります。
ステップ2:歌詞を確認して意味を覚える
歌詞を見ながら、分からない単語やフレーズの意味を調べて覚えます。
ステップ3:歌いながら練習
歌詞を見ながら歌ってみましょう。
最初は発音が難しくても、繰り返しているうちに口が慣れてきます。
ステップ4:暗記して歌う
最終的には歌詞を覚えて歌えるようにするのが目標です。
このプロセスを通じて、自然な表現や発音が身につけます。
好きな音楽を見つけて繰り返し聴きましょう。
なぜ洋楽や洋画なの?
なぜ洋画や洋楽を勧めるのか。
その理由は、英語だけでなく、何かを達成できない人の特徴は、「継続出来ない」から。
そしてその理由は「楽しくないから」です。
その為、英語を話せるようになるために必要なのは、「楽しく続けること」。
新たに言語を学ぶとしても、プロセスは日本語を身につけた流れと同じ。
「たくさん聞いて」「マネする」。
その為の手段としての映画や音楽なので、正直、楽しければ映画や音楽に縛られる必要はありません。
重要なのは、自分の好きなものを利用し英語に多くの時間触れることです。
「日常に英語を取り入れる」ことが鍵
従来の文法重視や問題集を解く方法でも良いですが、会話力を重視するなら日常的に英語を楽しむほうが効果的です。
特に、映画や音楽を通じて生きた英語に触れることは、実際の会話にも役立ちます。
私自身、「なぜ英語が喋れるのか」よく聞かれることが多いのですが、昔からアメリカ文化が好きだったこともあり、音楽や映画を通して自然と英語に触れる機会が多かったためだと思っています。
好きなものと英語学習を結びつけることで、楽しみながら継続できたことが大きいです。
まとめ
・言語習得には楽しく継続売ることが必須
・映画や音楽を活用しマネすると効果的
別の記事では洋画初心者におすすめの映画を紹介してますので気になる方は是非チェックしてみてください。
楽しく学べるコンテンツを見つけて、英語学習をスタートしましょう!
以上、最後まで読んでいただきありがとうございました。