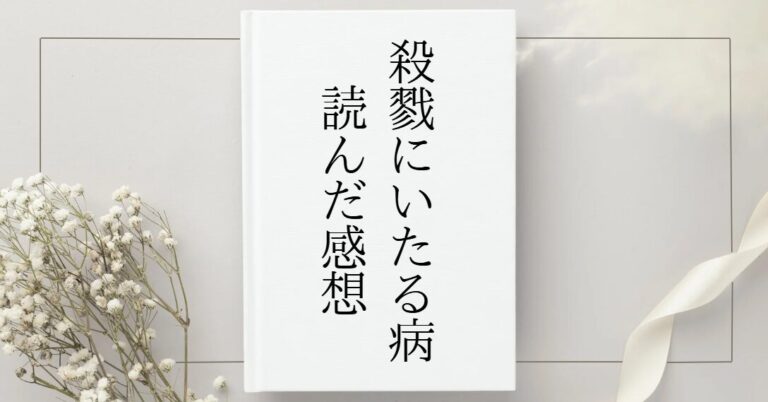あらすじ
東京で連続猟奇殺人事件が発生。
被害者は若い女性ばかりで、死体は凄惨な状態に解体されて発見される。
異常な手口に警察が奔走する中、ある青年が逮捕される。彼の名は蒲生稔。
穏やかで知的な雰囲気を持つ彼は、まるで日常会話のように淡々と犯行を認めた。「僕が殺しました」。
事件は解決したかのように思えたが、弁護士が調査を進めるうちに違和感を覚える。
彼の供述と事件の詳細が微妙に食い違っているのだ。
果たして彼は本当にすべての殺人を犯したのか、それとも別の真犯人が存在するのか。
この事件には想像を絶する「真相」が隠されていた。
読者の予想を裏切る衝撃の結末が待ち受ける、狂気と論理が交錯するサイコ・ミステリー。
殺戮にいたる病を読んだ感想
稔が殺人に至るまでの異常な心境を細かく書かれており、個人的には大好物でした。
そして、最後の展開と描写の破壊力。
著者の手の上で転がされていたような感覚で、ここまできれいな叙述トリックを体験したのは初めてだったのでとても感動しました。
息子の異常行動を観察していると思って読み進めていたのにもかかわらず、実はその父親の異常行動を探っていた…。大変見事でした。
初めて読んでから約一年が経ちますが、いまだに最後の衝撃と作品全体の面白さは心に残っておりとても良い作品に出会ったと感動しています。
読むならぜひ、事前情報が何もない状態で完読し、あの読書体験を味わってほしいと思います。
文庫版の解説を読んで
この作品のテーマには、「日本的な家族病理」があります。
母と子が過度に密着し、父は希薄な存在になっていき、正しい家族関係や距離感が歪んでしまっている。
この構図は、私自身も経験があるものでした。
母と子供である私たちの絆は、固く強く、お互いがお互いを求めていることが手に取るように分かるのですが、いまいち父親というのは、居ても居なくても変わらない気がして、何んともむなしい存在だなと子供ながらに感じていた時期がありました。
しかしこれって、比較的多くの家庭、もっと言うあら社会全体がうっすら分かってて、でも誰も口にしない事実なんじゃないかとも思うんです。
殺戮にいたる病では、この構図が立体的に体験でき大変興味深かったです。
しかし、解説を通さなければそれにすら気づけなかったのが悔しい点です💦
雅子の視点が息子ばかりに向き、それに違和感を持たなかったのは、父親がおざなりになることは当たり前の摂理だとどこかで認識しているからなのかもしれませんね。
まとめ
蒲生稔は、父親という側面を持つものの、未だに息子という面に多くを偏らせた人間だったようですね。
あの家には祖母、父母、子どもではなく、二組の母と子が同居していたという所が、最後によく表れており、後味残る作品でした。
こんなに綺麗にどんでん返しを体験させていただいてとても楽しかったので、ぜひ多くの方にも読んでいただきたい作品です。
この作品をきっかけに、叙述トリックを使った作品にとても興味が湧いたので、今後も良い作品があれば随時更新しようと思います。
以上、最後まで読んでいただきありがとうございました。